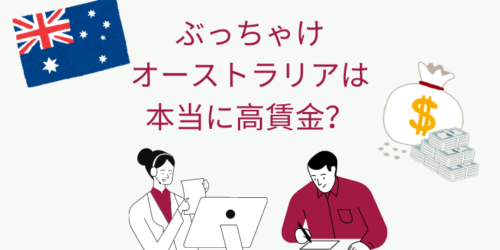オーストラリアで試みるキャリアチェンジ。コーディングコースがもうすぐ終わるのでその前にまとめてみる。

この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。
こんにちは。ジュークです。
2020年8月から始まった全24週のウェブ開発のオンラインコース (full stack web development bootcamp)も翌月半ばに早くも修了見込みとなっております。
実際の授業はすでに大方終了しており、残る3週間ほどは卒業課題への取り組みとわからないことがあればインストラクターに聞くことができる、そんな感じになっています。
インターネットで日豪問わず賛否要論のいわば「プログラミングスクール」「コーディングブートキャンプ」に実際に通ってみてどうだったか、そして1月頭より本格的に始めた就職活動についても触れてみたいと思います。
Contents
コースで学んでいること
本コースでは下記を学んでいます。
Browser
- HTML
- CSS
- JavaScript
- jQuery
- Bootstrap
- React.js
API
- APIs
- JSON
- AJAX
Dev Tools
- Heroku
- Git
- GitHub, GitLab
Database
- MySQL
- MongoDB
- IndexedDB
Server Side
- Templating Engines
- Sessions
- Writing Tests
- Node.js
- Express.js
- Creating APIs
- MVC structuring
- User authentications (login/sign-up)
- ORM (Sequelize)
Computer Science Fundamentals
- Algorithms
- Data Structures
要約すると、我々が毎日使用しているウェブサイトやウェブアプリに使用されている基本的な技術をカバーしている内容となっています。フロントエンドとバックエンド両方のコードの書き方や構造を学んでいるため、基礎中の基礎であるデータの挿入、データの取り出し、データの更新などをフロントとバックエンド両方をいじりながら行う、そういった基本的なウェブ開発を網羅しています。
カリキュラムとしては各トピックを2週間程度(毎週9時間くらいの授業があります)かけてカバーし、毎週課題に取り組みます。これに加え約3ヶ月に一回、チームまたは個人でプロジェクトに取り組み、コードを書き、完成したものをプレゼンしたりします。
通ってみてのぶっちゃけた感想
まず前提から
前述の通り、この手のコーディングスクールは賛否両論。特にツイッターの日本人界隈では特にあまり良い評判を聞かないのが現状となっていると感じています。以前も某鉄道会社をやめてプログラミングスクールに通ったは良いものの年収も待遇も下がり後悔しています、などといったツイートが話題となりました。
オーストラリアのネット界隈でも、「コーディングスクールより大学でITを学んだ方が就職機会は大きくないか」「こういったコースは無数とあって採用担当は毛嫌いしてる」などマイナスな評価もあったりします。
同時に、特に移り変わりの早いIT技術を大学で3年間、しかも仕事をやめてまで学ぶ必要があるか(パートタイムでも可能だが修了するまで5-6年必要となる)という議論もありますし、個々の経済的な状況や家庭の有無もあるのでこれまた一概には言えない側面があると思います。
逆にこういったコースではより実践的なスキルを短期間に集中して学べるというメリットもあります。特にフルタイムで働いてる人の参加が目立つのも、仕事を維持しつつ通えることが多いと思います。
よって、それぞれに良い部分と、あまりよくない部分があるのではと感じています。
私の場合、昨年11月に仕事をやめるまでフルタイムで働きつつ夜間に本コースに通っていました。仕事をやりつつスキルアップを目指し、「手に職」をつけてオーストラリア転職市場で自分の価値をあげていこうと思っていました。奇しくも11月に仕事をやめてしまいましたので今はこのコースが日々の主軸となっています。
「勉強した先に何を望んでいるのか」の落とし込み
さて、よく話題となる「この手のコースに通うのって無駄じゃない?」「本当にデベロッパーになれるの?」といった質問への私が実際に通っての所感をお伝えします。
「それを言ったら終わりだよ」と言われること請け合いですが、この手のコースに通って実際デベロッパーとして活躍できる人材になれるかは「その人次第」であるとは思っていますし、さらに「転職活動をしているタイミング」「探している仕事の条件」にかなり依存するとこのコースに通って再度実感しています。
これはプログラミングに限った話ではなく、どんな仕事を探すのにも「時間」「個人の意欲」「機会」が必要だと考えています。
例えば、現在のコースにも30人ほどが参加しています。年齢、性別、国籍、プログラミング経験の度合いもバラバラです。私のような全くの素人からのスタートの人もいれば、5年〜10年の経験者もいます(なんでいるんだろう、といつも思っています)
講師は経験年数二桁で百戦錬磨のウェブデベロッパー。アシスタントを勤める2−3名も経験十分な面々が揃っている印象で、カリキュラムもきちんと組まれており、それ通りに進んでいます。偉そうな言い方かもしれませんが「教える側」のレベルは十分に確保されていると感じています。
一方、特に悪くいうつもりはなく参加動機も人それぞれなので一概には言えませんが、コース参加者のおおよそ半分の15名は端から見ていると「とりあえず参加してみました〜」「デベロッパーになれたらいいけど必死こいて転職活動するつもりはありません〜」くらいの熱量のように見られます(それなりの学費を払ってるのになんでこんなテンション低いんだろうといつも思います)
この層は授業中も特に質問もしないですし、毎週の課題もちゃんとやっているのかよくわからないのが正直なところです(課題を一定数提出しないと落第になるのに…)
実際に死ぬ物狂いで勉強して授業中もアクティブに質問したり、インストラクターと個々の時間をとって学んでいるのは30人中、私を含めて5名ぐらいの感覚です。コース10週目くらいから積極的に質問する面々が固まってきたというのもあります。
参加者全30名の残りの10名ほども「転職できたらいいな〜」ぐらいの「受動的」な雰囲気で、宿題もやらなかったりグループ課題の時もやる気がないなど、本格的に学びに来ているとは感じられない側面もあったりします。
なので、こういった意味でも「人それぞれ」なんだなという印象です。
「使えるものは使う、使えるものを使えるようになる」
こういったコーディングコースではキャリアアドバイザーが就いたり、卒業前にデベロッパーの採用を考えている現地企業へのプレゼンや交流会などの就職活動の機会がある程度設けられているものが多い印象です。私の通っているコースもそういったものが提供されています。
具体的にいうと、キャリアアドバイザーは定期的に履歴書のレビューをしてくれたり、サポートチームが自分のポートフォリオサイトを添削してくれる、さらに面接などの選考に進んでいたらアドバイスや対策を教えてくれたりします。
確かにこういったサービスはとてもありがたく、私も十二分に活用させていただいています。同時に、こういったサービスの恩恵を最大限受けるには、個々が率先して履歴書を書いたり、積極的に転職活動を行い、多数の面接を受ける機会創出するモチベーションが問われているとも思います。もちろんコースを提供する側が履歴書を作ってくれるわけではなく、自分で作ったものを添削してもらうサービスなので、最終的には個人の意欲に依存となります。
企業へのプレゼンも、結局は個々のコミットメントが問われるわけですのでこれもまた人それぞれですね。最終的には、自身のプログラムの出来が企業への印象、そして就職を決めるわけですから。
私のコースではキャリアアドバイザーのサービスを使用しているのは参加者の半数以下のようです。それでなお、キャリアアドバイザーの文句やコース運営を批判するクラスメイトもいます。「なんだかな」とは思います。
批判はコーディングスクールに限った話ではない
私の感覚をまとめます。
例えば一流大学の法学部に行ったからといって卒業したら必ずしも弁護士になれたり、一流企業に就職できるわけではないのは誰にでもわかることです。もちろん一流大学を卒業するとその可能性は比較的高くなりますが、確約されているわけではありません。
この手のコーディングスクールは、一般的な大学で学士号を取ったりやMBAを取得しにビジネススクールに通うのと根本的には同じだと私は捉えています。教育機関はどこまでいっても「教育」を行う組織なわけで「職」を提供するものではありません。大学を卒業しても希望の仕事や会社に就職できなかったからといって大学が批判されることがないのと同義だと個人的には思います。
よって、こういったコースに通ってからすぐウェブデベロッパーになれなかったからといったコース運営側が批判されるのには個人的には違和感があります。
結局は、いかに環境を活用し機会を創出できるかが、その後の就職やキャリアアップにつながるものと思います。
なので私はいかにこの環境を最大限活用できるかを常に考えています。
私は基本的なところを大事にすべく、積極的に履歴書を更新してみてはレビューに提出したり、毎週の宿題は早めに取り掛かりわからないところはとことんインストラクターに納得するまで聞くなどしています。せっかく払ってる学費がもったいないし。
時間がゆるせば、課題の合格ラインに早めに到達しプラスアルファの機能をつけられないか独学で試みたりしています。
おかげさまで、インストラクターからも自分でいうのもなんですが名前を覚えてもらったり成績も上々の「A+」でここまできています。
したがってまとめると、「何を目的に通うのか」「モチベーションを維持できるか」の2つが大きな要素となっていると感じます。
就職活動のあれこれ
これまた大学と同じで、いかに良い大学を良い成績で卒業しても希望の仕事や年収を得られなかったら多かれ少なかれ本末転倒です。
2020年1月27日現在、このコースで学んだスキルで応募可能な求人に応募すること30件程度で面接2件、オファー0件が現状となっています。
オファーは現在ナッシングですが、1ヶ月弱の活動で毎15件の応募につき1回面接と思うと悪くない数字にも見えます。
噛み砕いて分析してみると、まず「経験年数なし」で応募できるデベロッパーの求人が当たり前のことだがとにかく少ない。なので「経験年数2年以下」ぐらいを目安として最近は履歴書を提出しています。提出するだけならタダなので。返事が来たらラッキーぐらいの感覚でいます。
フルタイム、パートタイム、カジュアル、インターンなど様々な雇用形態で探しては応募しているのが現状となります。
そのほか、Linkedinのデベロッパーコミュニティーに参加したり、Slackチャンネルに登録したりしています。こちらはすぐさま仕事を見つけるためというよりは「ネットワーキング」の側面が強いですね。
まだ1月で休み明けのため求人が絶対的に少ない時期なのか、コロナウィルスの影響で激減しているのか私にはコロナ前の経験がないので判断ができません。2月半ばぐらいまでは良い意味でも悪い意味でも様子見となりそうです。
純粋たるデベロッパー職に加え、これまでのセールスの経験を活かせるセールスエンジニアなどの仕事にも視野を広げて活動したりもしています。
終わりに
いかがでしたでしょうか。もし今後、特に海外でコーディングスクールに通う予定や思いのある方の参考になったらと思います。
長くなってしまいましたが、この手のコースの通う上で重要なものは、「自分が通う目的と動機の落とし込み」「あくまで教育機関であって就職確約ではない」「過度な期待はしない」の3つかなとは思います。
転職活動はただでさえ時間と労力が必要なものです。これに海外でのキャリアチェンジとなるとさらに骨が折れるのは火を見るよりも明らかです。なので長期的なスパンで見据えることも必要なのかなとは思っています。
「コースを卒業したらすぐにウェブデベロッパーになるぞ!」と意気込み、実際になれる人も一定数存在はするようです。私も少なからずそう思っていた一人です。しかしその一定数が「母数」に対してどれほどいるのかは未知数な気がします。
仕事探しが「楽」なことはどんな人でも職種でも業界でも珍しいでしょう。
コースが修了したらまたまとめ記事を書いてみたいと思います。
前回のまとめ記事もぜひご覧下さい。